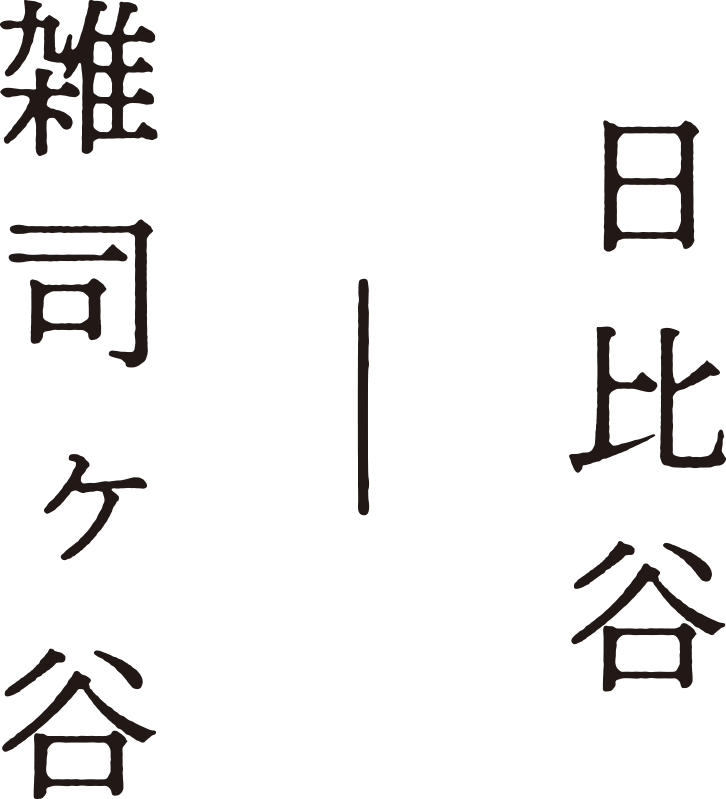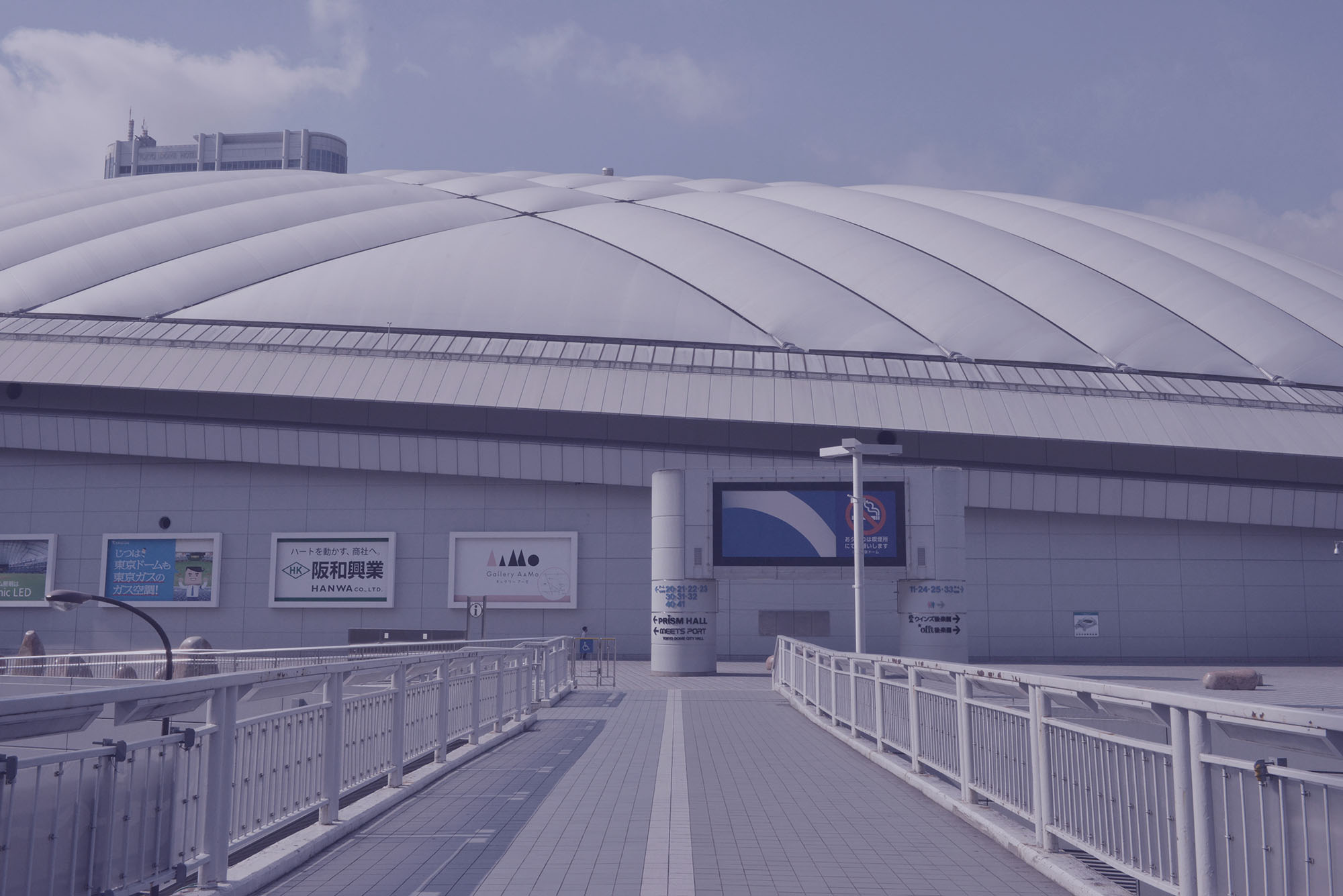初めて東京を歩いたのは、東京ドームがオープンする春だ。球場は完成していたものの、まだ試合は開催される前だったと、父から聞かされた。だからきっと、それは1988年の春だ。
物心がついた頃から、ぼくは阪神タイガースが好きだった。おそらく1985年に優勝する映像を目にして、野球というスポーツを理解するより先に、ファンになったのだろう。何かを好きになるきっかけなんて、そんなものなのだと思う。しかし、無意識のうちに阪神ファンになっていたとしても、野球が開催されているわけでもない東京ドームを見物したのはなぜだろう。保育園に通う子どもが「完成間近の東京ドームを観ておきたい」と言うだろうか。それを確かめようにも、東京ドームを見た日の記憶すら消えてしまっている。
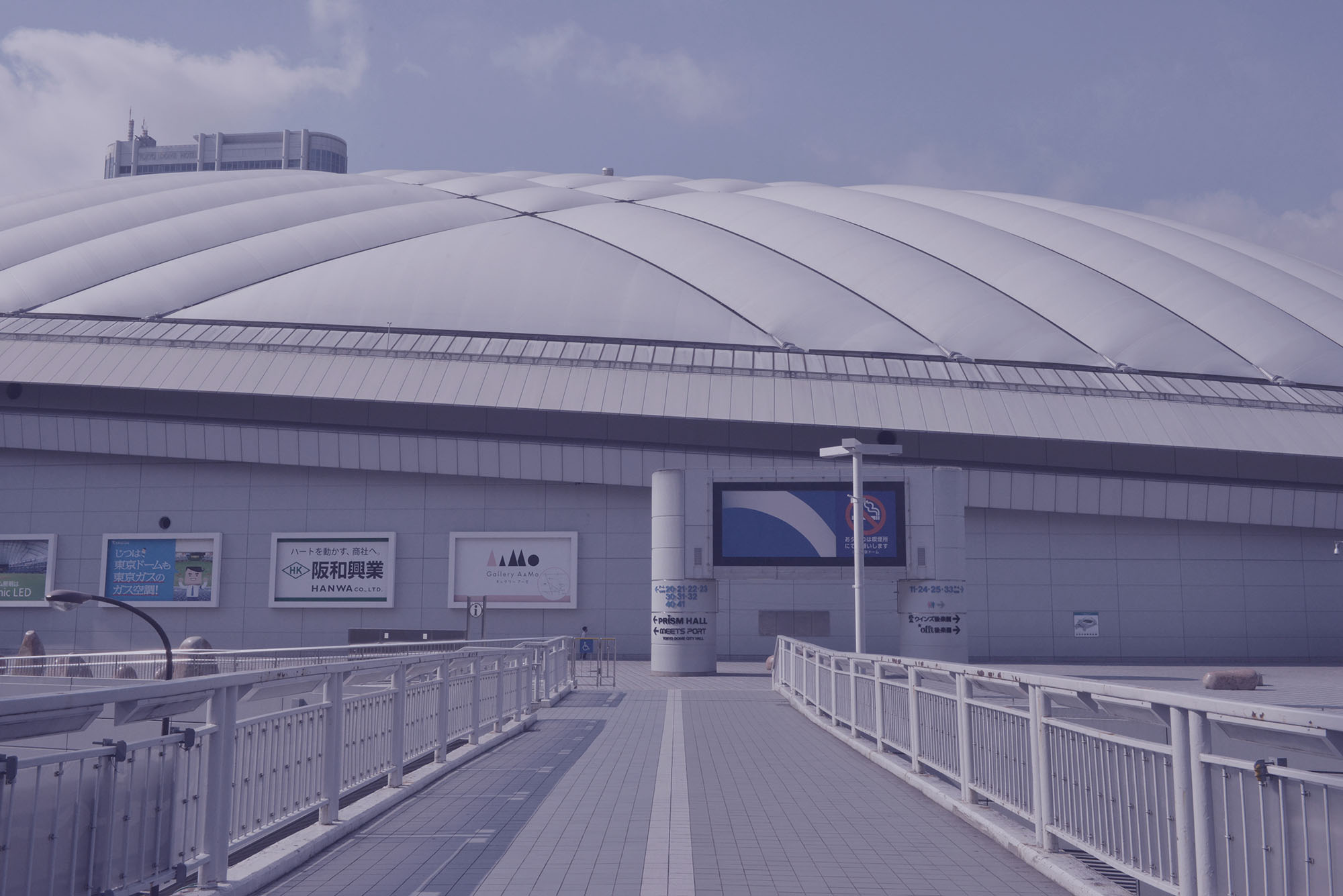
小さい頃の自分は、今の自分と同一人物なのだろうか。残っているのは断片的な記憶だけだ。
思い出すのは、納屋の中、ひとりきりで過ごした時間のこと。兄は近所のこどもたちと一緒に、田んぼにサッカーをしに出かけている。近所のこどもたちの中で最年少だったこともあり、ぼくはそれに加わらず、親に買ってもらったままごとセットで遊んでいた。キッチンを再現した、ままごとセット。マジップテープでくっついたにんじんを、おもちゃの包丁で切り分ける。小さい頃はままごとが好きで、女の子に間違えられることも多かった(今思えば、「女の子に間違えられる」というのも、時代を感じさせる話だ)。
5月、久しぶりに会った友人たちは『あつまれ どうぶつの森』の話で盛り上がっていた。ゲームの内容を聞きながら、小さい頃のぼくならきっと、夢中になって遊んだだろうなと思った。あんなにままごとが好きだったはずなのに、大人になって部屋を思い通りに飾られるようになった今、自分の生活にさほど興味を持てなくなってしまった。誕生日プレゼントにもらった花瓶は、花を飾るためではなく、ただ瓶としてそこにある。その隣には、ある演劇作品を観ながら飲んだハートランドの瓶が並んでいる。その演劇作品を観た時間は、とても印象深いものだった。だからといってその瓶が演劇を観た時間の証になるわけでもなく、他の誰かから見ればただの空き瓶なのに、どういうわけかずっと棚に並べている。
読売ジャイアンツのホームグラウンドは、かつて後楽園球場だった。そこまでは知っていたけれど、球場ができる以前に何があったのか、考えてみたこともなかった。そこには水戸藩の上屋敷があり、維新後はその区画がまるごと陸軍砲兵工廠になったのだという。砲兵工廠とは武器や弾薬を製造する工場である。
東京ドームは、土地の広さをたとえるのに使われる。それだけ大きな建物なのだから、小さな土地が地上げされて、建てられたのだとばかり思っていた(街を平らにして六本木ヒルズが造られたように)。でも、ここでは広大な敷地がその広さを保ったまま、別の空間に建て替えられたのだ。それも、徳川御三家である水戸藩の上屋敷という、旧時代を象徴する建物から、西洋から導入されたばかりの近代的な軍隊の施設という、新しい時代を象徴する建物に。
東京ドームを背に、北に進んでゆく。大通りから路地に入ると、細い道がやや蛇行しながら続く。そこにはかつて「小石川」や「千川」と呼ばれた川が流れていた。川だった場所が蓋をされて道となり、その上を歩いている。ここが暗渠になったのは、昭和に入ってからのことだという。

まだ水の流れが見えていたころに、この界隈を歩いた「私」がいる。
私はしばらくそこに坐ったまま書見をしました。宅の中がしんと静まって、誰の話し声も聞こえないうちに、初冬の寒さと佗びしさとが、私の身体に食い込むような感じがしました。私はすぐ書物を伏せて立ち上りました。私はふと賑やかな所へ行きたくなったのです。雨はやっと歇ったようですが、空はまだ冷たい鉛のように重く見えたので、私は用心のため、蛇の目を肩に担いで、砲兵工廠の裏手の土塀について東へ坂を下りました。その時分はまだ道路の改正ができない頃なので、坂の勾配が今よりもずっと急でした。道幅も狭くて、ああ真直ではなかったのです。その上あの谷へ下りると、南が高い建物で塞がっているのと、放水がよくないのとで、往来はどろどろでした。ことに細い石橋を渡って柳町の通りへ出る間が非道かったのです。足駄でも長靴でもむやみに歩く訳にはゆきません。誰でも路の真中に自然と細長く泥が掻き分けられた所を、後生大事に辿って行かなければならないのです。その幅は僅か一、二尺しかないのですから、手もなく往来に敷いてある帯の上を踏んで向うへ越すのと同じ事です。行く人はみんな一列になってそろそろ通り抜けます。私はこの細帯の上で、はたりとKに出合いました。足の方にばかり気を取られていた私は、彼と向き合うまで、彼の存在にまるで気が付かずにいたのです。私は不意に自分の前が塞がったので偶然眼を上げた時、始めてそこに立っているKを認めたのです。私はKにどこへ行ったのかと聞きました。Kはちょっとそこまでといったぎりでした。彼の答えはいつもの通りふんという調子でした。Kと私は細い帯の上で身体を替せました。するとKのすぐ後ろに一人の若い女が立っているのが見えました。近眼の私には、今までそれがよく分らなかったのですが、Kをやり越した後で、その女の顔を見ると、それが宅のお嬢さんだったので、私は少なからず驚きました。お嬢さんは心持薄赤い顔をして、私に挨拶をしました。その時分の束髪は今と違って廂が出ていないのです、そうして頭の真中に蛇のようにぐるぐる巻きつけてあったものです。私はぼんやりお嬢さんの頭を見ていましたが、次の瞬間に、どっちか路を譲らなければならないのだという事に気が付きました。私は思い切ってどろどろの中へ片足踏ん込みました。そうして比較的通りやすい所を空けて、お嬢さんを渡してやりました。
それから柳町の通りへ出た私はどこへ行って好いか自分にも分らなくなりました。どこへ行っても面白くないような心持がするのです。私は飛泥の上がるのも構わずに、糠る海の中を自暴にどしどし歩きました。それから直ぐ宅へ帰って来ました。
(夏目漱石「こころ」)
暗渠の上にある道路には今、千川通りと名がつけられている。通りを進んでゆくと、かつての町名を示す看板が出ていた。昭和39(1964)年まで、ここは「戸崎町」という名前だった。昔は川を伝って荷物を運んでいて、積み下ろしをする船が舳先を並べる様から「舳先町」となり、のちに「戸崎町」と改められたのだという。江戸は水の都と言われるけれど、こんなところにまで船が入り込んでいたのだと思うと、不思議な感じがする。
通り沿いに塀が続く。
塀の向こう側には何があるのかとまわり込んでみると、墓地が広がっていた。『こころ』に登場する「先生」は、毎月決まった日に「雑司ヶ谷の墓地にある或る仏へ花を手向に行く習慣」があったことを思い出す。墓が塀で見えないようになっているのは、墓に眠る人たちが往来の喧騒にまみれないためなのだろうか、それとも近隣に暮らす人たちの視界に入らないようにという配慮なのだろうか。

路地を抜けると小石川植物園があり、そこにも塀があった。塀で仕切られた道は、大通りに比べると気やすさがある。通りを歩く私に向けられるまなざしが、塀のある側は塞がれているからだろうか。気楽な気持ちで、より細い路地へと進んでゆくと、ご近所さんによる井戸端会議に出くわしてしまう。近所の人以外は通りかかることがないのか、一斉に視線を向けられてはっとする。
雑踏に紛れて、誰でもない誰かとして過ごせる。だから東京が好きだ。

不忍通りに出て、護国寺を通り抜けると、高速道路の高架で視界が遮られていた。その向こう側が雑司ヶ谷霊園だ。そこには夏目漱石の墓もある。
東京に出てくるまで、ぼくは卒塔婆を目にしたことがなかった。ぼくの実家がある地域は浄土真宗が強く、卒塔婆を立てる習慣がなかった。だから、テレビのコントでお墓に卒塔婆が立てられているのを見て、「あれは一体何だろう?」と、ずっと不思議に思っていた。
東京の霊園が不思議なのは、まるで公園のように整備されているところだ。東京府が雑司ヶ谷霊園を含む公共墓地を開設したのは、明治7(1874)年のこと。地方から東京に人口が流入するなかで、東京府は「朱引内」(江戸幕府評定所が定めた江戸の範囲)に墓地を新設することを禁じる布達を出す。そのかわりに、東京府が管理する公共墓地を整備したのである。当時の地図と照らし合わせてみると、公共墓地はどれも朱引の境界線付近に――当時の東京における都市と郊外の境界線上に――新設されたことがわかる。
雑司ヶ谷霊園に並ぶ墓には、さまざまな意匠が施されている。森謙二『墓と葬送の社会史』によれば、明治を境に日本の墓制は大きく変わったのだという。一口に墓と言っても、江戸時代まではさまざまな習俗があったが、明治に入ると平準化が進められることになる。明治7(1874)年に内務省地理局が発議した「墓地処分内規則」は、「死人ヲ埋メ木石等ヲ以テ其地ニ表識スル者之ヲ墳墓ト称ス」と定義した上で、その「墳墓」が「陳列一区画」をなしている場所が墓地であると定めた。つまり、単に埋葬地を「墓地」と呼ぶのではなく、「墳墓」の建立が前提とされたのだ。

ここで見られる墓地観は、墓地は「清き土地」に定めるものであり、その土地は「永久の潰し地」(永久墓地)であり、「死者の住処」であり、「祖先祭祀の場」であるというものである。したがって、遺体は損なうべきではなく、墓地をみだりに掘り返して改葬すべきではなく、したがって埋葬地を「捨て墓」とするような「両墓制」の習俗もまた否定されるべきものなのである。
(森謙二『墓と葬送の社会史』)
両墓制とは、遺体を埋葬する「埋め墓」と、死者を祀るための「参り墓」とを別個に設ける習俗だ。そこでは遺骨に対する感覚が、墓に対する感覚が、今とは異なっていたのだろう。しかし、いずれにしても、亡くなった人を墓で供養するという点では共通する。どうしてわたしたちは墓に手を合わせるのだろう。たとえば、亡くなった誰かが好きだった場所や、一緒に訪れたことのある場所で故人を偲ぶというのではなく、墓に手を合わせるのはどうしてなのだろう。ほんとうのところでは、それが理解できずにいる。かけがえのない誰かが亡くなったとき、遺骨に、位牌に、墓標に、その人が宿ると感じられるだろうか?
先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。依撒伯拉何々の墓だの、神僕ロギンの墓だのという傍に、一切衆生悉有仏生と書いた塔婆などが建ててあった。全権公使何々というのもあった。私は安得烈と彫り付けた小さい墓の前で、「これは何と読むんでしょう」と先生に聞いた。「アンドレとでも読ませるつもりでしょうね」といって先生は苦笑した。
先生はこれらの墓標が現わす人種々の様式に対して、私ほどに滑稽もアイロニーも認めてないらしかった。私が丸い墓石だの細長い御影の碑だのを指して、しきりにかれこれいいたがるのを、始めのうちは黙って聞いていたが、しまいに「あなたは死という事実をまだ真面目に考えた事がありませんね」といった。私は黙った。先生もそれぎり何ともいわなくなった。
(夏目漱石「こころ」)
ぼくは死という事実をまだ真面目に考えた事がないのだろうか。
雑司ヶ谷霊園を抜け、急坂を下ってゆくと、神田川にたどり着く。亀が甲羅を干している。神田川はすっかり舗装されているけれど、ここは暗渠にならなかったのだなと思う。塞がれた川と塞がれなかった川の違いはどこにあるのだろう。

川沿いに歩いていくと大通りに出た。そこには「江戸川橋」と看板が出ていた。こんなふうに地名が縦書きになった看板のことを「電停標識」と呼ぶのだと、最近になって知った。それは東京中を都電が走っていたころの名残りで、かつての停車場の名前が書かれている。都電が廃止されたあとも、「あの標識がなくなると、どこを走っているのかわからなくなる」という意見があって、今に至るまで残っているのだそうだ。

『こころ』が発表されたころ、都電――当時は「東京市電」といった――は新しい時代を象徴する乗り物だった。
主人公である「私」は、郷里で過ごしながら、「あの目眩るしい東京の下宿の二階で、遠く走る電車の音を耳にしながら、頁を一枚一枚にまくって行く方が、気に張りがあって心持よく勉強ができた」と振り返る。あるいは、病に伏せる父に対し、こんなふうに語りかける。
「そんな弱い事をおっしゃっちゃいけませんよ。今に癒ったら東京へ遊びにいらっしゃるはずじゃありませんか。お母さんといっしょに。今度いらっしゃるときっと吃驚しますよ、変っているんで。電車の新しい線路だけでも大変増えていますからね。電車が通るようになれば自然町並も変るし、その上に市区改正もあるし、東京が凝としている時は、まあ二六時中一分もないといっていいくらいです」
大正から昭和にかけて、市電の線路は都心から郊外へとぐんぐん伸びてゆく。『こころ』が発表されたのは大正3(1914)年はまだその途上にあり、ある路線の終点は江戸川橋であった。
わたしたちは、成長するにつれて、より遠くに出かけられるようになってゆく。
生まれたばかりのころは、ほとんど移動することもできなかったのに、歩けるようになる。そのうち三輪車に乗って、補助輪が外れて自転車に乗れるようになると、隣町にだって行くことができる。ひとりでバスに、電車に乗れるようになれば、より遠くの町まで移動できる。そうして年齢を重ねながら、わたしたちは速度を手に入れてゆく。だから電車の速度に驚くこともないけれど、徒歩しか移動手段がなかった世界から、突如として電車と出会った当時の人たちの目に、その速度はどれほど鮮やかに映っただろう。
中筋直哉『群衆の居場所 都市騒乱の歴史社会学』は、明治・大正期に形成された「群衆の居場所」のうち、「最も早くかつ最も頻繁に都市民衆の生活上の問題となったのは、大通りだった」と指摘する。
近世都市江戸の大通りはすでに一〇メートルから二〇メートルの幅を確保していたが、町ごとに木戸で仕切られており、また両側の商家が路傍に庇を張り出したり、定期市の屋台が真中を占拠したりして、実際には十全な幅と見通しを確保できなかった。(略)町々を貫く大通り上の自由な移動は、将軍や大名の行列か祭礼の神輿にのみ許されることであり、民衆は自分の町に留まって、それらを路傍より見物するばかりだった。
明治の大通りの変容は木戸の撤去から始まった。この改革は、社会学的には、町がその自治の基盤を近代国家に収奪され、形骸化していくことの象徴として把握されてきたが、町の周縁的な成員でしかなかった民衆にとっては、その規制力から解放されて、昼夜を分かたず町間=市内を自由に往来するという新奇な体験の可能性を開くものだった。
(中筋直哉『群衆の居場所 都市騒乱の歴史社会学』)
明治時代に造られた大通りは「改正道路」とも呼ばれる。その真ん中には「人の往来専用の交通機関が導入され」、「まず乗合馬車、ついで鉄道馬車、最後には路面電車」となり、「それらは人びとに徒歩では得られない速度と広々とした街区の展望をもたらした」と、『群衆の居場所』に綴られている。
東京には今、地下鉄が張り巡らされてはいるけれど、地上と地下ではランドスケープがまるで異なる。もう路面電車に乗ることはできないけれど、せめて同じルートを移動してみたくなって、江戸川橋でタクシーを拾う(思えばタクシーに乗るというのもずいぶん久しぶりの体験だ)。都電が走っていたルートに沿うようにと、「飯田橋から外堀通りに入ってもらえますか」と運転手に伝える。
飯田橋の交差点は右折できなくなっていて、少し迂回してからタクシーは外堀通りに入ってゆく。市谷見附に、四谷見附。これまで気にしたことがなく、ただ地名としか認識してこなかったけれど、「見附」とは何なのだろう。タクシーに揺られながら検索してみると、「見附」とは見張り番所を指すらしく、江戸城に置かれた主要な番所のことを「江戸城三十六見附」と呼んだのだという。タクシーの車窓からはお堀が見えた。そこが江戸城の外堀で、堀とはつまり、外敵の侵入を防ぐために張り巡らされた水路だ。15分ほど走ると、タクシーは虎ノ門にたどり着く。角を曲がると、そこに日比谷公園が広がっている。

今から100年以上前に、ここは騒乱の舞台となった。
明治37(1904)年に勃発した日露戦争は、両国合わせると10万人を超す戦死者を出し、膨大な戦費が注ぎ込まれた。戦争は日本側の「勝利」に終わったものの、賠償金が得られなかったことで民衆の不満が高まり、日比谷公園で講和条約反対を掲げる決起集会が計画された。危険を察知した警視庁が公園を封鎖したものの、群衆は公園に雪崩れ込み、暴動が発生する。日比谷焼打事件である。
明治38(1905)年の日比谷焼打事件から大正7(1918)年の米騒動に至るまで、東京では暴動が頻発している。この時期は「都市民衆騒擾期」と呼ばれ、政治意識の高まりの中で一連の暴動が起きたのだとされており、それが大正デモクラシーに繋がっていくのだと捉えられてきた。「都市民衆の生活意識に堆積した国家と独占資本に対する不満と反感が、国民大会への弾圧をキッカケにして警察への投石・焼打として一時に爆発した」のだと。
ただ、「この定説には二つの問題点がある」と中筋直哉は論じる。
第一の問題点は、群衆行動の形態に関するものである。定説は、群衆の大部分が投石や焼打の主体だったように考えているが、これは史料から考えても論理的に考えても、無理な推定である。そのことは、とりわけ焼打の主体について明らかだ。資料に見出せる焼打の「実行犯」は(略)明確に識別できる容姿、すなわち壮士姿をした少数の男たちであった。一方の群衆は、興奮気味ではあるがほとんどの者が見物するばかりだった。「論理的にも」というのは、焼打に必要な時間はわずかだから、立ち会えた者はごく限られていたはずだという意味である。いったん燃え上がった火はかなり長い時間燃え続けたはずだから、ほとんどの者は燃えさかる火を見物したことになる。焼打現場の群衆は凶悪な暴徒ではなく、燃えさかる火の見物人だったのである。
(中筋直哉『群衆の居場所 都市騒乱の歴史社会学』)
「第二の問題点」として挙げられるのは、群衆の暴力が向けられた対象だ。日比谷焼打事件で襲撃されたのは、警察署や内務大臣の官邸、政府を擁護する新聞社だけでなく、路面電車まで焼き討ちされ、群衆は「万歳を叫んだ」という。都市民衆に「生活上の不満」があったのだとしても、焼き討ちされる路面電車を見て「万歳を叫んだ」のはなぜだろう?
江戸の町人にとって、「大通りは、基本的には自らの町=家連合の、村の枠に準じるような枠づけられた内側の空間だった」。それが明治時代に入ると、木戸が撤廃され、改正道路を通って自由な往来が可能となる。ただしそこは、かつてのような「内側の空間」が解体され、「疎遠な交通の空間」になってしまったのだと中筋直哉は指摘する。さらに、そこには交番が配置され、通行人は国家の監視下におかれた。
(略)都市下層社会の住民、たとえば人力車夫や荷駄人夫などの路上営業者にとって、新しい大通りは無限に開拓できる自由さがかえって無限に開拓することを強いるような、肉体を切り売りする場所でしかなく、また職工や店員などの賃金労働者にとって、新しい大通りは心身をすり減らす職場へと連なる無味乾燥な通勤経路でしかなかった。彼らにとっても、新しい大通りは疎遠な交通の空間でしかなかったが、しかし、それを受容してはじめて、彼らの生活は成り立った。このような空間の構成要素であり、かつ都市民衆の目に最も映りやすい存在こそが、交番と路面電車だった。焼打とは、そうした存在を燃やして、群衆の目前に曝すことなのであり、それを遮らずに、むしろ興奮しつつ見物することは、疎遠な交通の空間が彼らの生活事実にもたらす暴力的作用に対抗するという意味をもった集合的暴力だったのである。
(中筋直哉『群衆の居場所 都市騒乱の歴史社会学』)
『群衆の居場所』が社会学の観点から日比谷焼打事件を捉え直しているのに対し、藤野裕子『都市と暴動の民衆史 東京・1905-1923年』(有志舎)は歴史学の立場からこれを捉え直す。ここでも路面電車が焼き討ちされたことに触れられており、「日常であれば退くのは民衆のほうであるが、暴動の場においてはそうではな」く、「引き返そうとしない電車を焼き払い、日常とは異なる力関係を示」したのだと論じられている。つまり、「電車に放火することをとおして、民衆は自らが大通りを占拠していることを実感した」のだ、と。
(略)民衆が日常から暴動へと飛躍する契機は、何よりも講和問題同志連合会にあった。しかしながら、政治集団と暴れる民衆とは「大正デモクラシー」という概念で一括できるほど同質であったわけではなく、むしろ民衆の独自性こそが暴力の基盤となっていた。その独自性とは、従来の研究が重視してきた、構造的に作りだされた貧困状態というだけでもなかった。民衆は日露戦争時の経験をもとに講和問題を独自に解釈し、行動しており、その論理は暴動のなかに色濃く表れていたといえる。なかでも、「露探」に見られるような、日露戦争期ならではの排除の論理は、民衆の暴力と密接につながるものとして極めて重要である。さらに民衆は一度成り立った暴力を用いて、事件前夜から培われてきた独自の講和反対の論理に基づいて行動を開始したほか、街路を占拠し、警察・教会に対する日常的な不満を表出するなどした。
(藤野裕子『都市と暴動の民衆史 東京・1905-1923年』)
ここに登場する「露探」とは、ロシアのスパイを意味する。
この言葉は戦時下に頻繁に使用され、新聞の投書などにも頻繁に見受けられるのだという。「露探」は売国奴とほぼ同義に用いられるようになり、国益に反する者に「露探」とレッテルを貼り、排除する風潮が生み出されていたという。民衆の独自の論理が暴動を招いたわけだが、この「暴動」とどう距離をとるのかが、日比谷焼打事件以降の政治運動の課題となってゆく。
(…)日比谷焼打事件の際には藩閥・官僚専制を批判するために「国民」の声を集めることが野外集会の目的であったが、結果的に起きた暴動は政府批判の材料に用いられる場合もあった。(…)大正初年においては、むしろ暴動が起きることを予測して屋外集会が開かれた。暴動が倒閣に発展することがあり得たからである。だが普選運動においては、暴動はこれまで以上に起きてはならないものになった。暴動の中心となった階層が選挙権を持つことを求める普選運動は、だからこそ屋外集会に彼らを動員しなければならない一方で、そこに集まった民衆は立憲的で模範的にふるまう必要があった。(…)
(藤野裕子『都市と暴動の民衆史 東京・1905-1923年』)
暴動の発生は国民の怒りのあらわれであり、野外集会の正当性を担保するものであった。ところが、時代が下るにつれて、暴動はむしろ野外集会の正当性を貶めるものになってゆく。そうした流れのなかで、野外集会を開く政治集団は、集会から暴力を排除しようと腐心する。その一方で、屋外集会を潰そうとする勢力は、暴動を起こす集団を送り込む。そこで動員されたのは、「男性」の「労働者」たちだ。彼らが暴動で噴出させたのは、「生活何の改善要求だけではなく、日常的に積み重なった男性労働者の疎外感と強烈な承認願望であった」。その暴力性は、さきほど触れた「露探」にもみられるように、「社会的弱者に対する蔑視や排外意識」を吐露する形で発露された。だから、『都市と暴動の民衆史』では、一連の暴動の最後に関東大震災における朝鮮人の虐殺を配置している。
それから100年近くが経過した今、日比谷公園には暴動の気配は感じられなくなった。まるで何もなかったみたいに、ただ穏やかな時間が流れている。
あのころに比べて、わたしたちの社会はよりまともになったのだろうか。「蔑視や排外意識」は、より強固に配置されているのではないか。それでいて、現状にNOを突きつけるために暴動を起こすこともできなくなっている。公園の近くには経済産業省がある、しかし日比谷焼打事件の頃のようにそこに向かって石を投げることはできなくなってしまった。

日比谷公園が暴動の舞台に選ばれたのは、偶然ではなかった。
明治に入ると、西洋から「公園」という概念が輸入されてゆく。多くの場合、寺社地が「公園」に改められていくのに対して、いちから創設されたのが日比谷公園だった。
江戸時代には武家屋敷があったその場所は、明治維新後は均されて、陸軍の練兵場となった。当時は東京唯一の練兵場であり、天皇が臨席する観兵式が60回も開催されている。明治19(1886)年に練兵場が青山に移転すると、市区改正事業の一環として、日比谷練兵場の跡地に公園を建設する案が浮上する。この公園は、単なる公園としてではなく、「国民広場」として計画され、明治36(1903)年に開催されると、日露戦争の「戦捷祝賀会」が何度となく開催されている。
日露戦争後、日本に凱旋する諸将の中で、熱烈に歓迎されたのは乃木希典だった。乃木は旅順総攻撃の指揮を執り、日本軍からは59000人もの死傷者が出た。旅順は近代的な要塞であり、攻略は容易ではなかった。攻略に苦戦するなかで、乃木に対する批判は高まり、乃木邸には石が投げ込まれ、切腹を求める手紙が大量に送りつけられた。だが、最終的には旅順を攻略し、それが日露戦争の「勝利」に繋がったことから、猛烈な歓迎を受けたのだ。
乃木希典の名前は、『こころ』にも登場する。
「私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。平生使う必要のない字だから、記憶の底に沈んだまま、腐れかけていたものと見えます。妻の笑談を聞いて始めてそれを思い出した時、私は妻に向ってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答えも無論笑談に過ぎなかったのですが、私はその時何だか古い不要な言葉に新しい意義を盛り得たような心持がしたのです。
それから約一カ月ほど経ちました。御大葬の夜私はいつもの通り書斎に坐って、相図の号砲を聞きました。私にはそれが明治が永久に去った報知のごとく聞こえました。後で考えると、それが乃木大将の永久に去った報知にもなっていたのです。私は号外を手にして、思わず妻に殉死だ殉死だといいました。
私は新聞で乃木大将の死ぬ前に書き残して行ったものを読みました。西南戦争の時敵に旗を奪られて以来、申し訳のために死のう死のうと思って、つい今日まで生きていたという意味の句を見た時、私は思わず指を折って、乃木さんが死ぬ覚悟をしながら生きながらえて来た年月を勘定して見ました。西南戦争は明治十年ですから、明治四十五年までには三十五年の距離があります。乃木さんはこの三十五年の間死のう死のうと思って、死ぬ機会を待っていたらしいのです。私はそういう人に取って、生きていた三十五年が苦しいか、また刀を腹へ突き立てた一刹那が苦しいか、どっちが苦しいだろうと考えました。
(夏目漱石「こころ」)
乃木希典は、明治天皇の大喪の礼がおこなわれた日の夜、妻・静子と共に自刃した。
どうしてその殉死は衝撃を与えたのだろう。
乃木は長州藩の支藩にあたる長府藩の藩士の子として生まれた。彼の生年は嘉永2(1849)年だから、19歳のときに明治維新を迎えた計算になる。つまり、幕末の動乱期に10代を送ったということだ。元治2(1865)年、長府藩士によって「報国隊」が結成されたとき、乃木もこれに加わっている。だが、戊辰戦争が起こり、報国隊が越後に進軍した際にはこれに加わらず、御親兵兵営でフランス式の操兵法を学んだ。御親兵になるということは、「藩の組織を離れて、新国家に帰属することを意味している」と、福田和也『乃木希典』にある。「つまり、ここで、明確に乃木は、報国隊など諸隊の同志たちと切り離されたのだ」と。乃木は伏見でフランス式の教練を学んだのち、長府に戻って徴募兵を教練する。
乃木が、隊伍を整え、分列行進をさせる。
どっ、と笑い声があがった。
見物に来た、旧報国隊の連中だ。彼らは、戦地をほとんど知らない乃木が、指揮をしていることを蔑んだ。だが、何よりもその、行進ぶりが、遊戯めいていて可笑しくて仕方がなかったのだ。大刀を担いで、北越の山野を駆け抜けた彼らにしてみれば、滑稽のひとことに尽きたのである。
ゆえに彼らは戦火の下での契りにこだわって、官僚的な近代軍に鋳なおされるのを激しく拒絶した。
一方の乃木は、戊辰戦争に参加しなかった。もともと、彼にとりついている孤影は、強い絆を、郷党との間に結ばせなかったのである。
といって、新国家と、強く結ばれていたかといえば、そうでもない。
たしかに、国家は彼を少佐に任命し、名誉と給与を与え、西洋式の操兵術を教えてくれた。だが、その国家とは一体何なのだろうか。現在、私たちは近代国家、国民国家と、平気で云うけれど、当時は誰も、もっとも確信犯的な建設社である大久保利通でさえ、その未来に定見をもっていなかったはずだ。
(福田和也『乃木希典』)
明治8(1875)年、乃木は小倉に赴任する。
この時代には、不兵士族による反乱が相次いだ。乃木は熊本鎮台歩兵第14連隊長心得として、明治9(1876)年に起きた秋月の乱と萩の乱を鎮圧する。乃木の弟・正誼は、萩の乱で反乱軍に与し、戦死した。また、乃木の師にあたる玉木文之進も、多くの門弟が反乱にくわわった責任を取って自刃した。つまり、「師と弟を犠牲にして責任を果たした」のだが、「その忠誠と功は報いられるどころか、逆に冷水をもって迎えられた」。陸軍大佐は書簡で乃木の戦闘ぶりを批判し、「長州ノ面目」にもかかわると非難した。挽回を期して臨んだ明治10(1877)年の西南戦争で、乃木は軍旗を奪われてしまう。
どうして乃木はそれほどまでに国に忠誠を尽くそうとしたのだろう。どうして「西南戦争の時敵に旗を奪われて以来、申し訳のために死のう死のうと思って」過ごしていたのだろう。軍旗とは「天皇から拝受した隊の象徴」であるにしても、当時の皇室の――国家の――権威というのは、まだ不兵士族による反乱が相次ぐ程度のものだったというのに。
江戸時代まで、戦うことは武士の特権だった。明治政府は武士階級を廃止し、廃刀令によって武士から刀を取り上げてゆく。こうして武士の特権が奪われたことが、不兵士族の反乱に繋がってゆく。
武士に変わって戦場に駆り出されることになったのは国民である。陸軍省から徴兵令が発布されたのは明治6(1873)年のことだ。
徴兵制というのは、かなり無理のある制度だ。
武士は、戦場で命を落とす危険があるがゆえに、特権が与えられていた。でも、徴兵される国民には何の特権も与えられていない。それなのに、どうして国のために戦わなければならないのだろう?
この無理難題を解決するために、乃木は「自らの徳義によって、それを補おうと決意した」のだという。
西南戦争で軍旗を失ってからというもの、乃木は連日のように料亭で痛飲し、放蕩の限りを尽くしていた。それが、明治20(1887)年のドイツ留学を境に、極度の禁欲主義者に変貌する。
不兵士族の反乱を鎮圧していた時代、軍に求められた役割は国内の治安を保全することだった。だが、時代が下るにつれて、外地での戦闘が求められるようになる。そこで「乃木が思い定めた道は、作戦なり、戦略といった軍の機能にかかわることではな」く、「いささか反時代的に、徳義を追求する道を選び」、「自らの生涯を絵筆として、理想の軍人の姿を描くこと」を目指したのだという。
乃木は一種の伝道者であった、と考えるべきかもしれない。
自らの存在すべてによって、訓えを広め、説得する伝道者であると。
たしかに、彼が広めようとした訓えは、つまり帝国陸軍の徳義と名誉の実態は怪しげなものだった。それは、にわか作りの、寄せ集めの、急場しのぎの体系のもとにつくられた陸軍を称揚する、いかがわしい宗教にすぎないかもしれない。けれども乃木は、そのことを知るからこそ、命を懸けなければならないと考えたのだ。
(福田和也『乃木希典』)
その乃木の前で、兵士たちはひたすら従容と死んでいったという。
本当だろうか。私には納得できない。
たしかに、愛国心はあっただろう。強い危機感も、国民は共有していたに違いない。ナショナルな連帯にもとづく高揚感もあっただろうし、農村を中心とする共同体がしっかりと残っていたから、国民は温順きわまりなかったかもしれない。
だが、燃えるような愛国心をもちながらも、命が惜しいのが人間という生き物だ。家族も大事なら、仕事も諦められない。金にも執着するだろう。
愛国的であると同時に利己的でもある人間たちが、なぜ、進んで死地に突進していったのか、その事をもう少し真剣に考えた方がいいと思う。
(同)
徳義を体現する乃木の存在があったから、兵士たちは戦地に向かったのだろうか?
仮にそうだとするならば、今の時代に、乃木のような人物がいなくてよかったと思う。「この人のために命を落としても構わない」と思う人がいたら、命を差し出してしまうかもしれない。戦争なんて二度と繰り返されるべきではない。ただ、それでも世界では戦争が繰り返されているし、国民の生活はあいかわらず国家に握られている。目の前に広がる穏やかな風景を眺めていると、そんなことはすっかり忘れてしまいそうになるけれど。
日比谷公園には噴水広場があった。噴水のまわりを小さな子が三輪車で走り、父親がそれを追いかけている。おだやかな休日だ。空はよく晴れている。昨日もよく晴れていたけれど、青空は飛行機雲で遮られた。「医療従事者に感謝を示すため」に、国が飛行機を飛ばしたのだという。

その日、飛行機の音が聴こえたので窓を開けると、そこにはもう機影はなく、ただ飛行機雲だけがあった。空を見上げながら、馬鹿にするなよ、と思った。
空に向かって石を投げても、自分の顔に落ちてくるだけだ。それがわかっているから、ぼくは石を投げることはできない。では、ぼくの憤りは存在しなかったことになるのだろうか。公園の売店は閉鎖されていたので、営業しているコンビニエンスストアを探して、缶ビールを買う。真っ昼間の公園で缶ビールを飲んでいると、どこかから白い目を向けられているような心地がする。あっという間に緩くなってゆく缶ビールを、自分の中にある違和感を確かめるように、ゆっくり飲み干した。